
生徒を改めて眺めていると寒々しい気持ちになるのである。陽の光はだいぶ春らしくなっているのに、教室は寒々しい。誰もやってこない教室ほど興ざめなものはない。すさまじきもの。
事務仕事が終わる
あれこれと学期末なので事務仕事が残っていたのだが、今日一日、邪魔されることなく集中してやっていると午前中には終わってしまった。普段がどれだけ中断されて効率が悪いことやっているのか……。
何はともあれ面倒な事務仕事が終わったので、ここから先は会議の連発である。生徒がいないことをいいことに、これでもかと会議を詰め込むのは何だろう?普段は会議をしていないのに、わざわざ会議をするのは時間をよほど持て余しているのか、普段はするべき会議をしていないのか……怖いから掘り下げるのはやめておこう。
事務仕事をやっていて腹が立つのは手書きが多いことである。イチイチ間違えるし、後から訂正が多すぎるんだよ!今回の場合、色々と配慮事項が後から増えていくので、出欠の訂正などが面倒なことになっている。
せめて、情報をちゃんと一括管理してほしいのだが……締め切りばかり言われるのでイライラするのである。
久々にずっと手書きで仕事をしている。それもまたストレスである。
課題の準備をしつつ……
休業になるのにあたって、こういう文章が文科省から出ている。
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報について
この中にこんな文章がある。
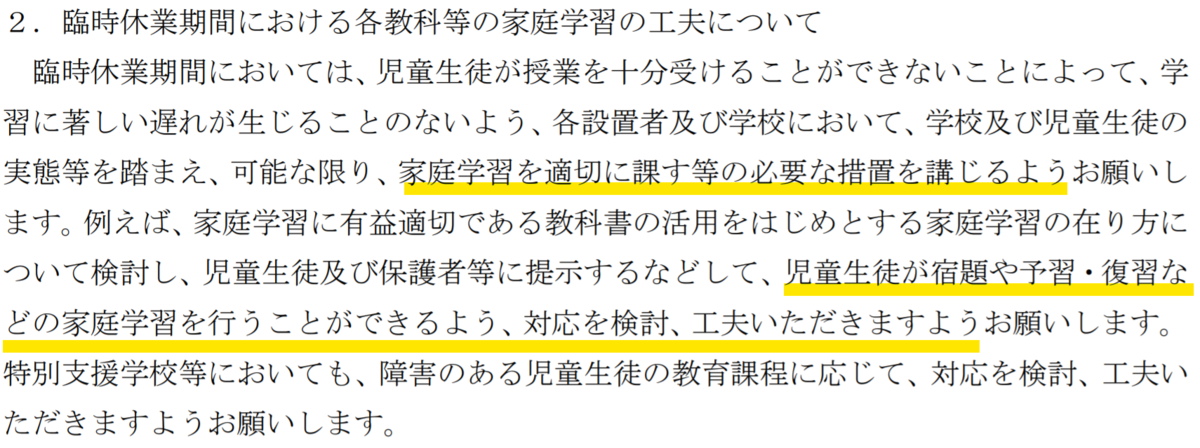
(下線は引用者による)
で、これに基づいて、「家庭学習を適切に課す」ことに躍起になっているのが、現状といったところである。
まあ、要するに春休みの宿題なんだけど。ただ、三月の授業が打ち切りになってしまっているし、上の文章の続きにあるように「新学期が始まってからの補修」はやはり現実的ではないので、どうにか三月の授業分をフォローしたいと思っているのである。
その結果、比較的、オンラインの教材を積極的に使おうという風向きが学校に吹き始めたような印象がある。
このような感じで、積極的にフォローしようという空気がある。
まさか、自分の身の回りで「積極的にICTを活用しよう」と管理職が言い出すとは思っていなかったので、急転直下でこんなに変わるとは思わなかった。
ウェブの教材を使うのは構わないのだけど注意点も多くある。例えば、豊福先生がこんなことを書いている。
学習者の学習活動全てを教員がコントロールすべき、という考えは、意気込みとしては良いかもしれないが、とても現実的とは言えない。
昨今の教育ICTは個別最適化が流行りだから、無料キャンペーンに乗っかって外部サービスを使ってしまえ、という発想にも待ったをかけたい。教材丸投げでやらせるだけなら、大量の学習プリント印刷配布と何ら変わらない。挙げ句の果てに「先生いらないじゃん」と言われたらおしまいである。
ICTは破壊的イノベーションである。

ブレンディッド・ラーニングの衝撃 「個別カリキュラム×生徒主導×達成度基準」を実現したアメリカの教育革命
- 作者:マイケル・B・ホーン,ヘザー・ステイカー
- 発売日: 2017/04/06
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
この本はこのタイミングで読み直されるべき一冊かもしれない。
【参考】
色々とここで気づいてしまったら、教員も生徒も使う前には戻れないだろうと思う。4月からどのように子どもと向き合っていくことになるのだろうか。






 このブログについて
このブログについて
