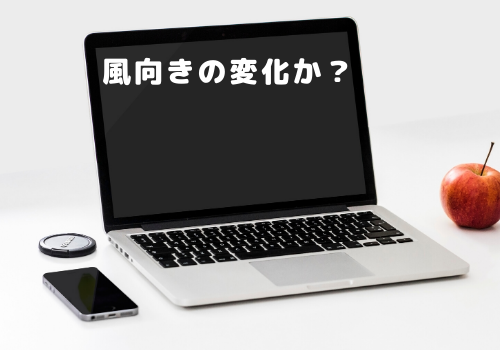
休業が始まって3日目。仕事もだいぶ片付いてきて、会議と根回しで時間を潰しているような感じになってきた。
そんな中、時間が増えた先生が多いので、少しICTに対する風向きの変化を感じるのである。
明らかに興味を持つ人が増えた
課題をどうやって伝えるか、プリントの配布もできないままに解散したし、さて、どうするかとなったときに、明らかにICTを活用してどうにかしよう!という雰囲気が出てきた。
勤務校の場合はスタディサプリを導入しているので、生徒へのメッセージ送信はできるのである。また、生徒からも活動メモを活用すると、課題の提出もできるので何とか使ってみようという話が出てきている。
これまでログイン率でみても、なかなか厳しかったところなのだが、ここに来て毎日、色々とログインして機能を確かめる人が増えてきた。
まあ……分量を考えていきなり生徒に配信して押し付けても、ろくなことにはならないのだが、一応、学年で調整しながら出題するということになっているので、まあ……大丈夫だろう。
それよりも自分の担任しているクラスに、色々とメッセージを送ってみたり細々とした連絡事項を送ってみたりと活用し始めたのが良い傾向であろう。
これで「ちゃんと使える」という話になったら、もう少し日常的に気軽に使うようになって紙を減らそうという話になる……かな?
少なくともムダな配布物をやめようという話にならないだろうか。
時間があるからか…
少し、仕事も落ち着いてきたので、今のうちにやれることをやろうという話ができそうな段階にやってきた。
このあたりの情報量もかなり増えてきて、ニュースなどでも報道され始めていることもあり、普段はあまりICTに詳しくない人であっても、こういう動画サービスなどを話題に挙げるようになってきた。
さすがに、管理職はアカウントの登録などには慎重な態度を示しているが、登録不要なサービスについては少し使わせてみたいという気配も見ている。
昨日も紹介したが、いよいよこの本を職員室においてみても読んでもらえるかな?という気分になってきた。

ブレンディッド・ラーニングの衝撃 「個別カリキュラム×生徒主導×達成度基準」を実現したアメリカの教育革命
- 作者:マイケル・B・ホーン,ヘザー・ステイカー
- 発売日: 2017/04/06
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
スタディサプリの授業のレベルも、実際に自分たちの目で確認するようになると、「あ、これ授業を動画に任せてももしかしてよいの?」ということに気づき始めている人がいる。
100%を代替することはできないけど、ショートカットになりうるということに気づいて「じゃあ、授業で何を教えればいいのでしょう?」という話題が出始めている。
自分たちの授業が相対化されるということに気づいて、「少し工夫をしてみよう」という話が出てきているのは良いことのように思う。自分たちの授業の手札が増えるように感じてもらえるのはよいことだろう。競合していく部分もあり、協奏していく部分でもあるのである。
期待値の高まりが逆に怖い
こうして少しずつもしかしたら「ICTって使えるかも?」という気配が出てきたものの、それだけに生徒が生徒指導事案を引き起こしたり思いのほか学習の効果が得られなかったりしたときに、かえって大きな拒絶をされそうな予感もしている。
それだけに、ここからの活用の仕方は勝負所だなぁと思っている。
これは自分の学校だけの問題だけではなく、色々なところで起こりうることだろう。どうか、よい活用の事例が共有されていき、失望されることがないように……。





 このブログについて
このブログについて
