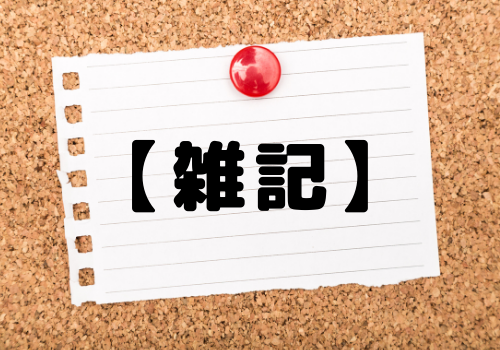
BYODで授業を続ける。三年前と違ってリテラチャーサークルをしながらデバイスを利用する生徒がほとんどだ。
そうなるとちょっとした話合いに変化が。
ギクシャクの原因
話合いの能力を決める要素は多岐にわたるので断言は出来ないのだけど、どうもデバイスを手に持って話合いをしていると、ギクシャクする感じがする。
別に「スマホが悪い!!」と言いたいわけではない。
ただ、話合いの様子を見ていると、スマホがあることで少し失敗することがある。
というのも、相手が発言したときに悪気無く何かを調べるためにスマホの画面を見たり集めてきた資料を確認するためにスマホの画面を見たりすると、そこで話合いのテンションが下がるのである。
行動自体は別に紙の本を読み直したりノートに書き込みをしたりするのと違いがあると思わないのだけど、何だろう?確実にスマホの画面やパソコンの画面を見ると、話合いのテンションが下がっているように見えるのである。
相対的に、スマホの方がテンションの下がり具合が大きいように感じるので、一番の原因はプライベートとパブリックがBYOD端末だと切り分けられていないことが大きいのかもしれない。
また、生徒も自分もスマホの用途が非常に娯楽に寄っているイメージがあるせいか、話し合っている時にスマホに視線を移されると、自分が無視されたように感じてしまうのかもしれない。
余談ですが、授業でスマホを使っていると、生徒の首が心配です。自分が首を傷めているので余計に…ね。
健康被害とまでは言わないけど、まあ、色々と注意は必要です。ただ、根本的にはちゃんと大きな画面のタブレットやラップトップを準備すれば軽減される問題だと思うので、過渡期と言うことで…。
強制させたらやっていられない
話合いの時に「スマホを使うな」というのは簡単なのだけど、LMSを通じて集めた生徒相互の情報を、話合いの時にこそ使わなければ意味が無い。また、話し合っていることをどんどんリアルタイムで書き込んでいくから、他の班にも情報が共有されるという流れになるので、スマホを使って記録するなというのもイマイチな感じがある。
生徒だって、必要がある、良さがあるから話合いの時にチマチマとスマホでコメントを書いたり編集したりしているわけで、単純に「使うな」と強制するのであれば、そもそもICTを使う必要は無かろう。
紙での話合いだって、話している相手を目の前にして紙の本を読んだりノートを書いたりするんだけど…なぜ、どうしてこうも質的に話合いの雰囲気が変わるのだろう?
色々と生徒の様子をじっと見ていくしかないかなぁ。







 このブログについて
このブログについて
