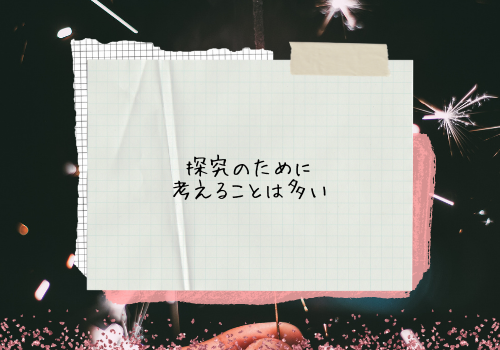
次年度からいよいよ新学習指導要領が始まり、探究学習も本格化する。
しかし、なかなか現状の様子を見ていると苦しい状況も見えてくる。
検索は難しい
一人一台ICT端末の環境が整備されつつあるので、授業中に簡単に教室の外側の情報にアクセスできるようになっている。
しかしながら、それにあまりに頼り切りになると、探究の時間中、延々とスマホを検索し続けるような展開になるし、それが一年間延々と続くことに……。
そして、検索して手に入れた情報であっても、決して信頼できる情報ばかりではないというのは言うまでもない。
実際に、授業で生徒が検索している様子を見ると、想像以上に何か情報を得るためには検索が汚染されているように思う。相対的にWikipediaがマシに思えるほどには、安易なGoogle検索は使い物にはならない。
最近は、ベネッセなども含めて多くの業者が学校での探究のノウハウを貯めて、書籍などにまとめているので、CiNiiやGoogle Scolarなども使われるようになっているので、その点では少しずつ進歩していると思われる。
でも、普段から使っている人であればよく分かるけど、論文検索をしても必ずしも自分の知りたい論文を閲覧できるわけではないし、そもそも論文だとは言え、その質が優れているとは限らないのだ。
もちろん、高校生までの能力では読むことは難しい。確かに、自力で論文を読んで…という事例は見聞きすることになっているが、放っておいて勝手に論文が読めるようになるのではなく、時間をかけて一緒に読むトレーニングをしているから、自力で読めるようになっているという事実を見落としてはならない。
探究の第一歩のような検索から躓くような状況にあるのが、学校の現実だろう。
その意味だと、今週末に発売になる次の雑誌は結構注目している。
「高校の」探究は、本気でやればかなりのことが出来るに違いないと思うのだが、そのためのノウハウがまだまだ暗中模索である。どこまでたどり着いているのかを読めるのが楽しみである。
教科でトレーニングを
おそらく、いきなり探究だけ断絶して探究を行うことは出来ない。
そのためにも、おそらく各教科の「探究」という設置科目何だろうけど、探究する気が教員にあるかどうか。受験のための応用科目程度にしか見てないよな
— ロカルノ (@s_locarno) 2021年11月7日
高校の各教科に「○○探究」という科目がいくつか入り混んでいるが、間違いなくそれは総合的な探究のために必要なスキルのトレーニングの要素が入り混んでいる。各教科の資質・能力のトレーニングと教科の枠を超えた真正性の高いトレーニングが入れ小型になっているイメージ。
でも、現状の高校だとこれらの探究と名の付く選択科目はただの入試のための応用練習の科目にされていくんじゃないかと危惧している。
いい加減、教科に固執していくことからは離れるようにならないかな……こだわると固執するは違うことなのだ。





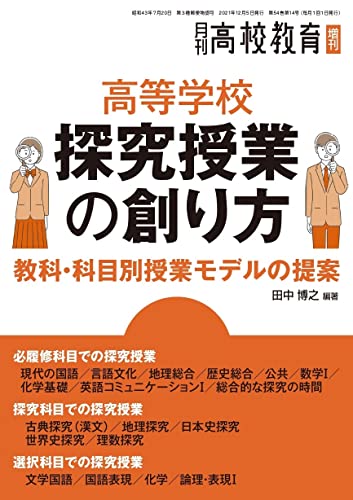
 このブログについて
このブログについて
