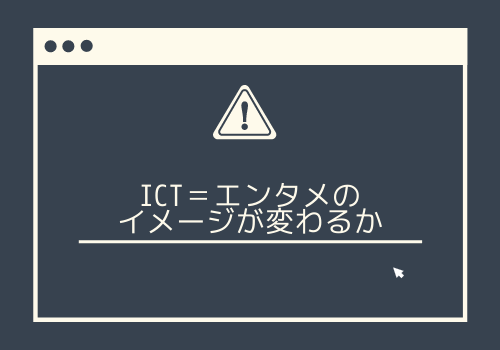
こんな記事を読んだ。
日本の場合はデジタル機器を使っていないわけではないけれど、その用途がエンターテインメントに偏りすぎている、というのも非常に大きな問題だと感じました。
(2021/11/30確認)
これはPISA2018の結果を受けて、比較的、ICT教育界隈ではよく言われていることである印象である。
実際、生徒の様子を見ていると、スマホに振り回されがちという話はよく分かるし、だからこそ、使い方をどうするかというデジタル・シティズンシップ教育が話題になる。
学校も教員もどう接し方を教えれば良いかということは手探りなところです。
子どもはコントロールできないか
この問いは非常に難しい。
やはり色々と魅力的なコンテンツが揃っているのがオンラインの世界であるので、その魅力にあらがうことは、発達段階によってはかなり難しいのではないかと感じることはある。
いきなり手放しで生徒にアプリ使い放題……とはならないし、実際、発達段階を考慮して必要な制限を計画的に準備する必要がある。
ただ、いつまで経っても管理を続けていくような運用ではやがて破綻をする。
必要な制限を入れつつも、制限を自分自身の判断でコントロールできるように、早めに指導できることが望ましいと感じる。
ただ、制限して使わせないということは、自分自身を律するというコントロールを学ぶことには繋がらないし、許容可能な失敗をくり返しながら学ぶように促すのが教育の仕事ではある。
子どものコントロールの能力は決して高くはない。でも、侮って取り上げるような指導がよい訳ではないのだ。
ICT=エンタメというアレルギー
だからこそ、コントロール出来るように必要な権利を与えていかなければいけないと思うのだが、その際に大きな壁になるのが「ICTを与えたら遊んでばかりでとんでもない」という大人のアレルギー反応である。
子どもがICTデバイスを見つめていること自体に嫌悪感があるような場合もあるので、なかなか一筋縄に行かないところである。
実際、子どもは多くの場合で使い方に失敗すると思う(指導経験上、残念ながら避けようがないと思う)ので、その上でのコントロールやリカバリーの仕方を学ぶのが合理的だし、必要なことだろうと思う。
失敗を上手く許容可能な失敗にコントロールして、指導することが仕事になってくるはずなのだが、なかなか失敗を許容できないのが大人の世界なのである。
かつてこういう本が既に出ている。
まあ、ここまで大人を煽るのは、オススメしない。それでも、色々な提案や事例がGIGAスクールの影響もあって、蓄積されているように感じるので、丁寧に情報交換を続けて「これくらいの失敗なら許容できるかな」というラインを見つけて、粘り強く向き合うしかないのだろう。
授業で創造的になろう
エンタメ消費に走る一つの理由が、「暇つぶし」なのだろうと思う。
空白の多い時間を持つから、ICTで時間を潰すのである。だからこそ、授業でICTを作ってコンテンツを作る楽しさや圧倒的にアウトプットできることに挑戦したいところだ。
授業で表現したいと思うことが増えてくるとよいなぁと…ぼんやりと思っている。







 このブログについて
このブログについて
