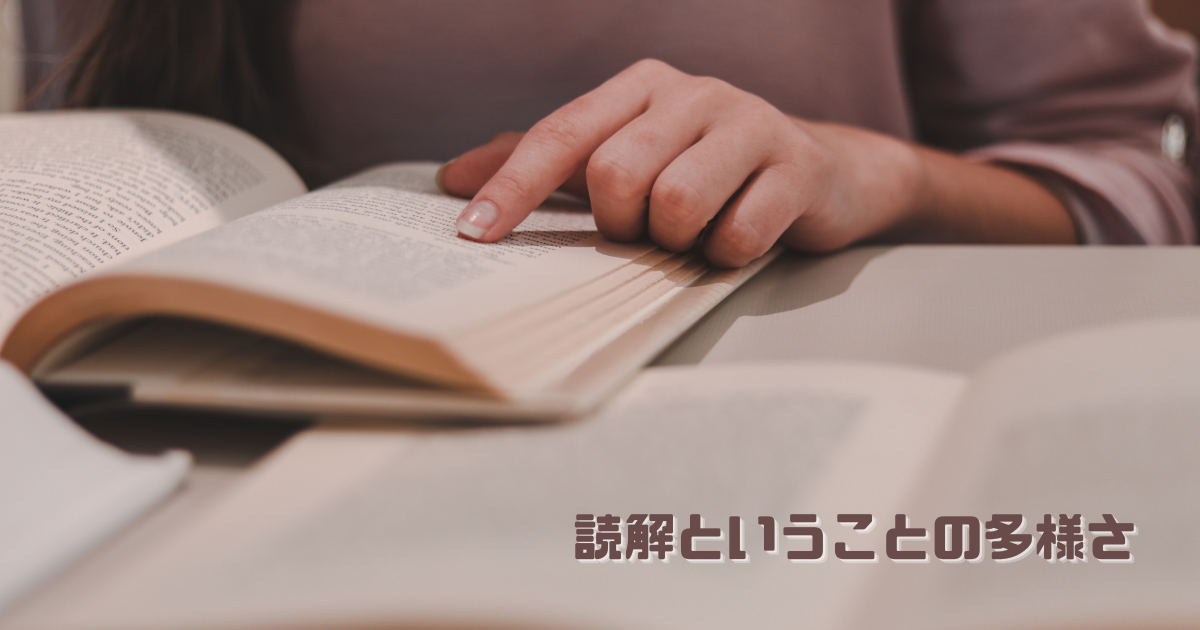
本日は小ネタの紹介です。
ゆる言語ラジオで紹介されていたので目を通したけど、国語の先生も必読ですね。https://t.co/9X3Ytr65j2
— ロカルノ (@s_locarno) 2022年7月2日
Twitterでも紹介しましたが、今井むつみ先生の新刊がとても面白いです。
タイトルが「算数」なので国語科の先生方はスルーしがちな気がしますが、「読解」ということを考える時にこの本の内容はとても刺激的です。
ゆる言語ラジオ以上の書評は無理…
ゆる言語ラジオで、今井むつみ先生をゲストに招いてこの本の話をしている。
もうね、ご本人が登場して解説している上に、思わず人に話したくなるような内容は全部語り尽くしてしまっているので、この動画以上の書評はすぐには書けない。
とにかく、動画を見て欲しい。動画を見るのが大変ならばVoicyから耳で聞けば良いので!!
算数の文章を読むということが、どのような行為なのかということを説明してくれているので、この本の面白さが伝わるはずです。
読むということを考える
動画の中でも触れられているが、この本のタイトルを読むと、新井紀子氏の本を思い出す。
そういえばこんな記事を前に書いていましたね…。
RST界隈については、誠実に研究している方もいることは把握しているので、あまり先入観であれこれと言いたくないが、上記の記事でもあるように、不誠実な記述が多く、批判に対する回答が見えてこないということもあって、あまり良いイメージがない(興味を失っているので、その後の研究の展開を追いかけていないので、どうなったのかは最近の事情は知らないので、もし何か展開があるなら知りたい)。
だから、『算数文章題が解けない子どもたち』というタイトルを見たら、非常に警戒する気持ちが出てきたが、似ているのはタイトルだけで問題意識の置き方は別物でしたね。
子どもの読むことの発達段階の複雑さを感じさせられる本です。なかなかすぐに授業にノウハウとして「こういう発想をするからこういう練習をすればよい!」という観点として活用するべきかは難しいところであるが、子どもの読解には子どもの理論があることを教える側が把握して、様々な授業や単元を準備してみることに意味があるのではないかと感じる。
AI本の方がRSTのごり押しに見えてゲンナリとするのに対して、もう少し、余裕を持って色々な見方をするときに役に立つだろうと感じる一冊だ。







 このブログについて
このブログについて
