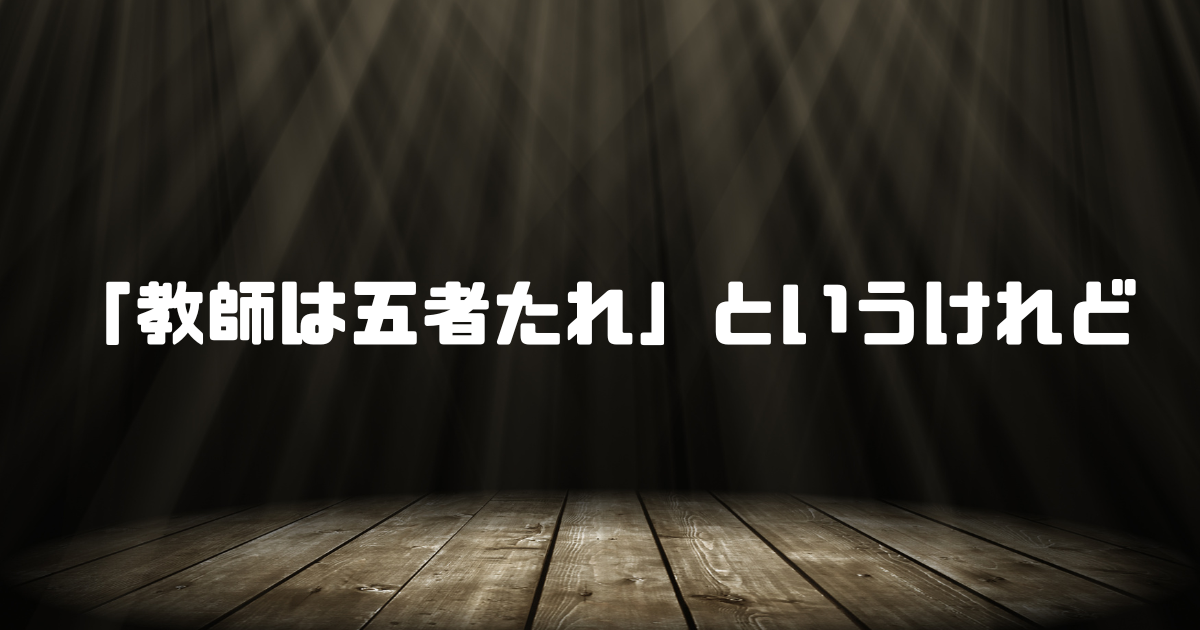
珍しく本日は休み。
SNSを眺めていると学期末と言うこともあって教員界隈が荒れているなぁという印象。
そんなこともあって「教師は五者たれ」という言葉を何となく思い出して色々と考えていた。
そもそも五者とは?
「教師は五者たれ」という言葉で言われる「五者」とは以下の通り(諸説あり・後述)。
学者…教科の力を付ける
演者…授業の魅力する
芸者…生徒に寄り添う
易者…将来を見通す
医者…生徒の悪いところを取り除く
「教科の授業だけやってればいいわけじゃないんだよ」という戒めみたいな言葉である。
もちろん、「学者」として教科の専門性はなければいけないし、「演者」として授業で生徒を引きつける技術も必要だろう。それだけでなく、生徒の成長と進路を支えていくために「芸者」「易者」「医者」としての役割も果たしていく。
そういうイメージとしてのこの言葉は実感として分からないでもない。まあ「芸者」という言葉が教育現場に適切かどうかみたいな話は置いておくけど。
現実の教員は……
「教師は五者たれ」という言葉の意味が分かると言ったものの、この言葉は今の現実の教員には即していない。
なぜなら、理由は単純明快で「教員の仕事は五者どころではなくなっている」からということに尽きる。
最近、様々な文脈で教員の過重労働が話題になっているが、SNSで教員が担っている仕事を拾い上げていくと、もはや何が専門なのかが分からなくなるのもよく分かる。
どこまでが教員の仕事なのかという議論は難しい。
結局、最後は人間を相手にしている以上は、「勤務時間外なので」と割り切れるようなものではないし、小原國芳ではないけど全人教育的な面が今の学校教育の強みでもある以上、学者と演者以上の仕事を担うからこそ授業で実現できるものもある。その良し悪しは議論しづらいが、子どもたちをよく見ている教員達に支えられて今の学校があるのは事実である。
(その意味では、安易に教員免許を持っているが現場から離れている人間を教員として人手不足対策にしようという考え方は、学校と教員になる人の間のニーズが上手くマッチせずに、上手くいかないように思う。)
一体、自分が何を仕事しているのかはよく分からなくなるのは割と日常茶飯事でもある。
仕事を手放さないといけないと思いつつも、手放せない理由も分かる。
五者は多いか少ないか?
現実問題として教員の仕事は「五者」どころではないのだが、実際、教員の仕事は何者くらいなのだろう?
仮に、校内の分掌や生活指導などを担わないで「授業」だけをすることを想定すると、現在の非常勤講師の働き方がこれに近いように思う(とはいえ、現実的には「授業だけの契約」のはずの非常勤講師であっても、子どもたちのあらゆる生活に関わって教育しているのが現実だ)。
しかし、「授業だけ」をするとしても自分の肌感覚からすると、授業のために「医者」や「芸者」や「易者」の役割は必要な気はする。授業で言葉を伝えるときに、どのように子どもたちと向き合っているかは伝わる。飛び込みの一回切りの授業であっても、敏感に教室は反応するのだから、日常的に長く関わっていくとなれば、誤魔化しはきかないだろう。
まあ…こういう話をするときのイメージはほぼ一斉授業のイメージである。そもそも、個別に学んでいくという形になっていくときに、「五者たれ」というような言葉はなくなっていくのかもしれない。
雑談
「教師は五者たれ」ってどこが言い始めたんだ?と思って調べていたら、レファレンス協同データベースに登録があった。
「教師は五者たれ」ってあったなと思って調べたらマジか。 https://t.co/MwsUJX2Mvr
— ロカルノ (@s_locarno) 2022年7月18日
司書の調査能力は他に真似できないような専門性ですね。








 このブログについて
このブログについて
