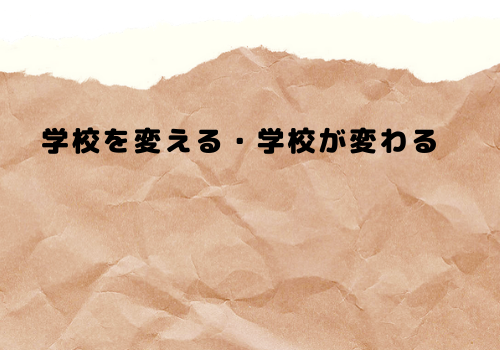
生徒が登校してこないと17時退勤が出来る……訳でもないくらいには働いている状況ですが、長時間労働で自分のことが出来ない悪循環をどうにかしなければいけないと思っている。
ちょうど新年度に向けて、生産性向上に関する一冊が出てきたので早速読んでみました。
大分大学附属小学校の「学校を変える」というプロジェクトの全貌が分かる一冊です。
仕事を減らすことが目的ではない
本書は大分大学附属小学校の「学校改革」の道のりが、当事者の説明や関係者のインタビューによって描き出された一冊である。
教育業界にいればよくご存じの通り、「国立大学附属学校」は不夜城と揶揄されるくらいには、学校経営や教科指導については激務と多忙を極める世界である。一流の先生方が莫大な時間と自分の生活を差し出すことで成り立っている天上の世界……そんなイメージがある?
少し言い過ぎた感はあるが、実際、国立大学の附属学校は、地域の教育をリードする拠点としての機能もあれば、歴史と伝統を持っているために、周囲からの期待を集める学校であることは間違いない。その裏返しとして、教員の多忙化と激務化がつながっている……と外側にいると、そのように見えるのである。
実際に、本書の冒頭に述べられている話が、そういった附属学校の激務ぶりであり、その激務のせいで教員が疲弊し、新しい異動を希望する人が減り続け、一層に疲弊が加速するというような悪循環が述べられている。
このままだと学校が立ち行かなくなるという危機感を持ち、校長先生の強いリーダーシップによって、改革が断行されたということが述べられている。
この「学校改革」は、確かにスタートには「業務を減らす」という目的が含まれていたのは間違いない。しかし、それは目的の一部であり、ゴールそのものではないのである。
詳しくは本書を読んでもらいたいが、「業務を減らす」ということが「子どもの生活や学びを向上させる」ということにも繋がっているという明確なビジョンがある。そして、地域の期待にもきちんと答えようという附属学校としての誇りがある。
近年の教員の働き方改革の話を聞いていると、どうしても「研究授業」などが槍玉に挙げられやすい。
しかし、ある意味で「よい授業」「新しい可能性のある授業」、そういうことを考えることは、教員としてのプライドに関わる部分でもある。それだけに、「生産性」だけで今まであった教員のプライドやこだわりまで質を下げてしまう必要はないのである。
この大分大学附属小学校の取り組みは、決して期待値の下方修正ではないのである。教育に対する願いとプライドを持ちながらの、断固たる改革なのだ。
ひたすらに「スクラップ」……だが
しかし、それでも肝に銘じておかねばならないことは、本書の改革の多くは「スクラップ」であるということである。もちろん、ビルドのことも一つではないのは事実であるが、「スクラップ」が8割以上を占めている印象である。
「良いものがあればやってあげたい」というのが、教員の基本的な心情である。そして「前例踏襲」は学校の常であり、学校に長くいる人が管理職よりも権限がある……なんてことはザラである。
しかし、そういう「学校の中の慣例」に対して、厳しく妥協することなくメスを入れたのが、大分大学附属小学校の取り組みなのである。人員の異動の話とかはなかなか「うぉ…」と思ったりしましたが…。
がんじがらめになって動けないと思っているものが、校長のリーダーシップと適切な組織作りが出来れば、思い込みとは裏腹に少しずつほぐされていくのだ。そういう凄さがある。
大分大学附属小学校の取り組みで特によいと思ったのが、教員の意見の集約の仕方である。学年主任を中核として若手の意見を吸い上げつつ、適切な部署でその意見を議論するのだという流れが理解できる。もちろん、本書で紹介されているように、その組織の機能が上手くいかないで諍いが生じたこともあったようであるが、結果的に、組織が動いているのは、組織作りが上手かったからと言えるだろう。
教員は腹を割って議論するのは苦手だ。何か議論になる前に、根回ししておいてさっさと議論になる前に決着をつけようとしてしまう。その結果が、暗黙の了解と前例踏襲で増えていくばかりの仕事であるとも言える。
何かを改革するための議論をすると、組織の中でハレーションは必ず起こる。そのハレーションを聞いていると、改革しようとしている人が色々な可能性を吟味できていない頭が悪い人間のような話し方をする人も少なからず出てくる。
しかし、それは根本的には感情的な対立でしかないし、真正面からの議論や意思疎通をしていなかったことの結果に他ならない。
この本に書いてあることを再び何となく思い出すのである。
一人が突っ走ってもダメだし、誰かを非難してもダメなのだ。
個人的には絶望感もあり…
大分大学附属小学校の先生方が色々な対立や苦労を乗り越えて、少しずつ改革に成功していったという姿には非常に感銘を受ける。なるほど、学校もちゃんとビジョンとエビデンスで運用していけば、合理的な組織として動けるのだと。
しかし、その一方で、自分の身の回りのことを思わざるを得ない。
ビジョンとエビデンスというが、そのビジョンとエビデンスを理解できるのは、子どもの学びの力の向上と生涯の幸せを本気で願うからである。
もし、議論のスタートが「子どもの幸せ」であるということが共有できないのであれば、このような取り組みは可能なのだろうか。
今、多くの学校の職員室で起きていることは、文字通り死にそうになりながら働いている教員が多くいる一方で、ブラックなんて言葉はどこ吹く風で、倒れそうな人を見ないふりしている教員が混在しているということである。
ここまでいうと少し悪辣だなと我ながら思うものの、学校内の、職員室の中の仕事の量が公平に、平等に、割り当てられているか。諦められている教員がいないと言える人はどれくらいいるのだろうか。
今の自分は、「ビジョンとエビデンスが共有できない」ということのハードルの高さに絶望感を抱いている。
一方で、こうして悪者を作り、自分を当事者から外しているような物言いをする自分にも嫌悪感がある。
たかだか、一個人の教員に何が出来るというのだろう?
それでもなお自分に出来ることをやる
正直、気持ちは重い。
しかし、自分は当事者なのである。だから、自分の出来ることをやりつづけ、周りを巻き込み続けるのである。
学校に関わる当事者が自分なのである。
意見を聞いてもらえるくらいのことは、続けなければと思う。
私学勤めだからいざとなれば学校を移ればいいとも思う。でも、教え子たちの母校はここしかないのである。母校が誇れないようなことになったら、子どもたちには不幸であろう……だから、やれることをやれる限りやるしかないのだと思っている。
そろそろ新年度が見えてくる。自分が疲弊せずに、何を続けようか。







 このブログについて
このブログについて
