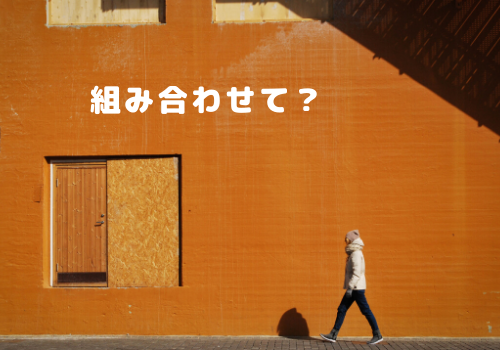
ICTの無かった状態には戻させないよ。
使えるもので授業を変える
生徒が登校してきているが、ここで一層、ICTを授業で活用していこうと思ってどさくさに紛れて色々とやっている。
配布する資料の半分くらいはオンラインだけに切り替えているところから始めて、細々と色々な作業をICTで取り組んでもらっている。もちろん、手書きで試験は受けることになるから、手書きの作業もさせながらである。
生徒の端末に頼っているので、実質的にはスマホがほとんどなので、分量を求めるような作業はやっぱり厳しい。このあたりはラップトップをちゃんと揃えないとダメなんだとつくづく感じる。…金銭が厳しい。
毎回の振り返りをオンラインに移行したら、生徒へのフィードバックの量が格段に増えた。手書きで作業するのと同じ時間で倍の情報は流し込める。その情報量が生徒にとって好影響を与えるのかはまだ分からないけど、量をかなり担保できている。
これまでは印刷物の都合でなくなく省略していた説明を詳細に書いてもよいと思うようになったし、生徒に提示できる情報は確実に増えている。
逆に言うと、大切な情報がどんどん流れてくるから、どう受け止めようかという生徒の迷いが若干ある。このあたりは少しずつかな。
必要な情報は全部生徒に隠し立てせずに最初に出してしまう。その上で、どう使うかをガイドしつつ、最後は生徒自身に選んでもらえればいいかな。
自動化を活用したい
オンラインの確認テストは、選択式の問題とは非常に相性が良い。自動採点どころかあらかじめフィードバックの文言まで用意しておけるので、完全に今まで紙で集めて夜なべして採点していたものを自動化できる。
非常に楽であるし、今まで眠らせていた指導書付属の確認テスト類も、全部生徒に情報として提示できる。使うかどうかは生徒に任せつつも、授業の解説を簡略化しても大丈夫な部分を増やせそうだ。

ブレンディッド・ラーニングの衝撃 「個別カリキュラム×生徒主導×達成度基準」を実現したアメリカの教育革命
- 作者:マイケル・B・ホーン,ヘザー・ステイカー
- 発売日: 2020/05/22
- メディア: Kindle版
本当は、ブレンディッドラーニングといえるくらいに個別化して、それぞれのことを選べれば良いのだけど、機材の不足や設備の不足もあって実現が今すぐには厳しそう。ただ、授業時間内に基礎トレーニングするか、応用の文章作成するかなどを選べるくらいの自由度を生徒に持たせてあげられるのがよいかなと思う。
教科によっては難しさもあるけど……まあ、工夫次第ではないか。
よいと思ってもらうために
よいと思ってもらわなければ、その先はない。死蔵されていく運命にある。
生徒から「まったく使わなくなった授業があるのに、教室で自由に使っているのは斬新だ」なんてことを言われたが……それじゃあ困るのである。
備えると言うことは、恐れるということでもある。でも、生徒がいるのだから、楽しくやろうと思う。楽しく意欲が出るのであれば、それを見て、真似をしたくなるのが教員という集団である。
結果を出してしまおう。






 このブログについて
このブログについて
