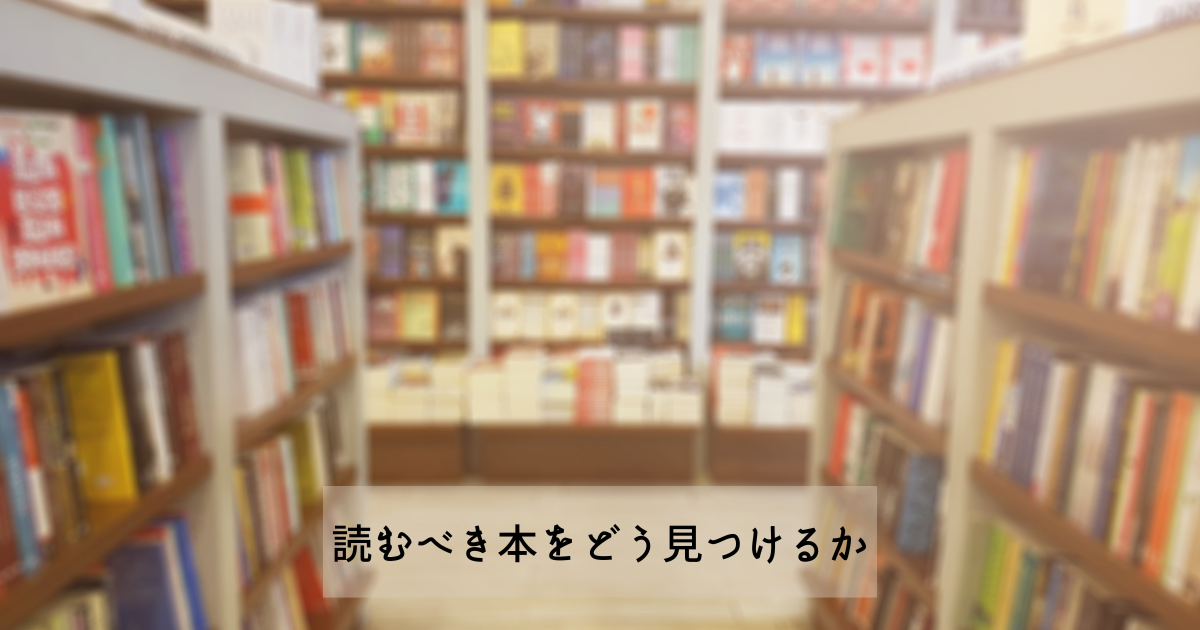
地元の書店に立ち寄ったら「オンライン立ち読み」として、flierが活用されていたのを見つけてちょっとビックリ。
本の隣にQRコードがあり、その本の要点を示しているページが簡単に閲覧できるようになっている。以下の記事はちょっと古いけど、イメージとしてはこれ。
上の記事は2020年なので、一見すると「販売」するには逆効果になりそうな気がするのだけど、わざわざPOPなどを作ってアピールしているところを見ると、販促にそれなりに効果があったのだろうから、今になっても継続的に行っているのだろうと思う。
読むべき本が多くてどこから手を付けるべきか、悩むところである。
要約サイトは一期一会
読むべき本を探しているときに、要約サイトは個人的にはほぼ参考にならない。それはジャンルがビジネス書に偏っていることや要約されているものを見ると、欲しい情報や話題はだいたい終えてしまうため、かえって買ってまで読まなくなる。
とはいえ、ちょっとした時間に無料で手軽に閲覧できる範囲を眺めていると、時々、ピックアップしておこうかな?という本にも出会うことがある。
要約サイト経由で購入した本は、消化も早い。
だいたいの内容を要約で把握しておきつつ、なおかつ自分に比較的興味があるテーマの本だからこそ、ストレスなく早々と読める。
逆に言えば噛み応えはないので、自分の知識を広げたり深めたりという読書にはならない。例えるならば重湯のような読書になるので、あまりこの手の読書を続けていると、授業づくりのネタとしても幅が狭くなる。
追っておきたい情報を手軽に見つけるくらいの使い方がちょうど良い。
レコメンドに乗せられる
結局、本の購入のルートで一番多いのが、Amazonなどのサイトで本を買うと、次から次へとレコメンドされるため、そのレコメンドを参考に購入することが多い。
「人のことをよく知りもしないで薦めてくるなよ!」なんて反骨精神は自分にはないので、レコメンドされたもので自分の興味関心があればついつい買ってしまう。
結果的に、積ん読を溜め込むことになるのだが……。
ただ、レコメンドされたものを買い続けていると、自分の場合はどうしても教育書ばかりになる。
注意深く、教育書以外の本も買うようにはしているのだけど、どうしても購入量が多いので、それをひっくり返すような薦められ方はされないので、傾向に偏りがあるよなぁ…などと感じている。
その意味では、Audibleには教育書はほとんど存在しないので、全然、関係ないジャンルを聴取していることが多く、レコメンドで出てくるものが本家のAmazonとは違っていて面白いところ。
Audibleで聞けるので購入しないかと言われると、そうでもない。
いかんせん、オーディオブックだと一冊に10時間とかかかるので手早く読んでしまいたい時には向かない。
そのため、割と気になった本は書籍を購入してしまうことは少なくない。
リアル書店
読書の幅を広げるにはリアルな書店に行くのが一番である。
新刊の情報も新刊のコーナーに行けば一目瞭然であるし、関連する書籍もきちんと陳列されているので一目瞭然である。
自分の専門に購入する本が偏りがちになるという問題も、棚を意識して広く買い集めれば、解決が出来る問題である。
ただ、残念ながら東京や大きな都市に出ないと、書店の規模が小さく、専門性が高まれば高まるほど、買うものが見つからなくなる。
自分などは東京まですぐに出られるので、本気で読むものが欲しいときは東京に出るが、結局、地元の書店では欲しいものを見つけることはかなり難しい。
足繁く通うことができる大型の書店があるかないかによって、見える世界は大きく変わってしまうのだろうと思う。
大学のそばにはそれなりの大きさの書店はあることが多いので、やはり大学生のうちにリアルな書店に足を運ぶ癖をつけておきたいものだ。
積ん読の方が多い…
本を選ぶという問題よりも、積ん読の方が多いという問題が…。






 このブログについて
このブログについて
