新学期が始まりまして、学校の業務も通常営業。
少し、教科でも次期指導要領について、今後、どのように向かっていくのかということを話す時期になりました。
ちゃんとまとめようと思っているが…
高校の学習指導要領解説が出ているのは分かっているし、ある程度読んだのだけど、まだブログにきちんと考えをまとめてなかった。
なんだか、試案が出た段階でまとめたからいいかなーと思っていたら完全に気を逃した。
このくらいしか書いてなかった……。まあ、異論反論も出てきているところなので、もう少し趨勢を見守ってから書こうかなと思います。
わかっていたけど…
一番、話していて大きな壁として感じるのが、「そもそも学習指導要領を読んでない&読めていない」ということである。
「現代の国語」と「言語文化」に分かれるので、「現代文」「古典」で分業は難しくなりますよーという話をしても「え、別に教科書から抜き出しでそれぞれの担当が教材をやればいいんじゃない?」と言われるのです。
それはダメなんじゃないかなぁー……世の中がいったいどのようにやるつもりなのかは分からないけど、結局、今までのように「読むこと」偏重で、「現・古分断」の授業を高校がやり続けたら、いよいよ狙い撃ちにされて、もっと縛り付けがきつくなるんじゃないかなぁ……。
割と、文科省に近いところの人は、注意深く辛辣に「現・古の分断、分業」を退けているように見えるし。
第3章のQ&Aで、現場の教員の「苦情」をやんわりと却下しててかなり踏み込んだなぁと思いました。例えば「古典に加えて、近代以降の小説も「言語文化」に含めた理由は?担当配置が難しくなる!」→「そもそも現行の国語総合だって分けて学ぶことは求めてねぇわ!」など。 pic.twitter.com/7zi1RFKLlO
— ロカルノ (@s_locarno) 2018年9月2日
そもそも「現代文」「古典」を分業で持つというのが、非常に「教員の都合」での理論である。もちろん、それぞれの分野の専門性は否定しないけど、「国語」という形で、「現代文・古典」を全体を俯瞰する立場だからこそ、きちんとそれぞれの分野の価値を伝えることや文化の継承をバランスよくできるのではないか。「国語教育」としての観点ではなく、「古典」だとか「現代文」だとかの立場からの議論を教員がし始めたら、お互いにお互いの教えていることが素晴らしい!という泥仕合にしかなるまいよ。
「子ども」「国語としてふさわしい素材」「社会」の三者を俯瞰してつないでいき、成長をうなすことができる見取りをできるのが、国語教員の専門性とは呼べないか。そのためには、大学のような「専門」に閉じこもる方向での、悪く言えば似非研究者ぶった授業は、「国語科」の仕事ではないのではないか。

灘校・伝説の国語授業 本物の思考力が身につくスロ?リ?ディング
- 作者: 橋本武
- 出版社/メーカー: 宝島社
- 発売日: 2011/11/21
- メディア: 単行本
- クリック: 28回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
この授業をほめる国語の先生は多いけど、自分としては「国語科の授業」とは呼べないだろうと思う。まあ…灘の生徒にとっては、一番切実に意味があることなのかもしれないが、一般化して理想の国語だと言われれば、それは違うというだろう。
高校の実践例が増えてきたこと自体が…
今度の学習指導要領は、読めば読むほど根本的に科目としてのあり方が問い直されてしまっている。良いか悪いかの議論はこれからされるだろう(まあ…もっと前から答申は出ていただろとは思うのだが)し、一つ一つを議論するほどまだ深く読めていない。
自分の立場としては、高校の国語がこれだけ狙い撃ちされていることを重く受け止めて、もう少し、「国語」のあり方を広く、豊かに考えていいのではないかと思う。
割と、「実用」という言葉にアレルギー反応を起こしている例を多く見ていますが、「実用」という話は、現行の学習指導要領で一気に増えましたのだし、平成10年度学習指導要領にも出てきていますから、まあ……唐突に出てきた話ではないのと、内容自体も決して「変な」ことは書いていないと思うのだけどなぁ……その話と文学の圧縮は切り離して考えないとはた目から見るとおかしく見えるのではないか。
まあ、話を元に戻すと、これだけ大きな変更なので、高校の指導案が載せられた教育書がかなり増えたという印象がある。たとえば

高等学校国語科 新科目編成とこれからの授業づくり (シリーズ国語授業づくり)
- 作者: 町田守弘,幸田国広,山下直,高山実佐,浅田孝紀,大滝一登,島田康行,渡邉本樹,日本国語教育学会
- 出版社/メーカー: 東洋館出版社
- 発売日: 2018/08/10
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
だとか

アクティブ・ラーニング時代の古典教育 小・中・高・大の授業づくり
- 作者: 河添房江
- 出版社/メーカー: 東京学芸大学出版会
- 発売日: 2018/02/05
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
だとか
だとか
だとか……。
雑誌でも
珍しく高校の実践まで掲載されたり。
まあ、学習指導要領関係ないとも言えますが、アクティブラーニング絡みで出てきたものですから。
高等学校の実践が、小中に比べてあまりに世の中に出ていた本が少ないことを思えば……まあ、ショック療法でも授業を見直していこうと、本の数自体が増えることはよいことなのではないかと思うのです。
さすがに今までの高校の積み重ねが破壊されるかの言い方は煽りすぎかなぁと。釘をさすべきところもあるでしょうが、今までの「読むこと」偏重に陥っていた高校の国語科のままではいられないのではないか。
それこそ、どこまで「実用」に対する責任を引き受け、どこまで「文化遺産」の継承に対する責任を受け持つのか……それを現実的に提案できるのは現場のはずである。その現場が、意固地に「読むこと」偏重を続ければ、それこそ破滅的な外圧に遭うのではないか。





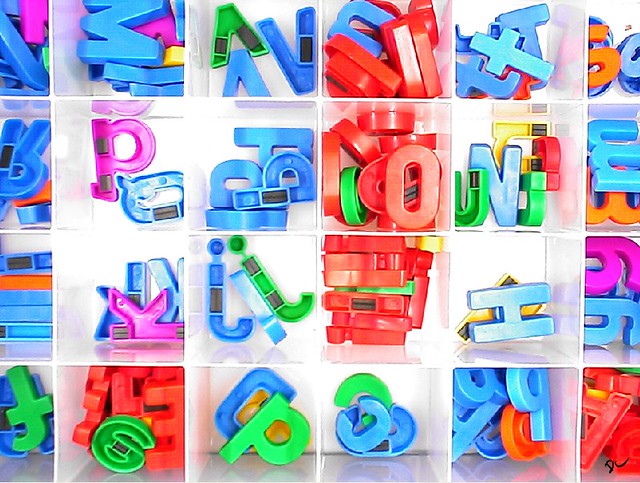




 このブログについて
このブログについて
