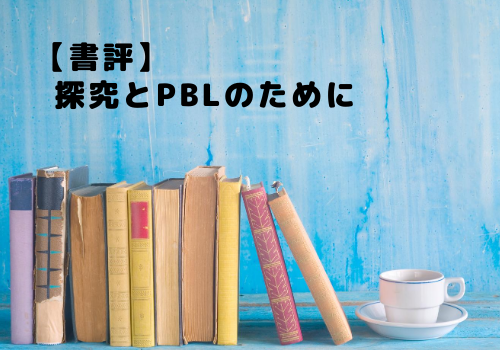
夏の読書シリーズ第一弾。
最近発売したばかりの稲垣忠先生のPBL本を読みました。
明治図書から出ていることもあって多くの人に読みやすい一冊になっています。
良書の条件を思う
教育書は毎月大変な冊数が出版されているので、その全てを追いかけることは当然ながらできない。できるだけ目を通すようにしたいと思っているけど、金銭が無尽蔵にあるわけでもないので、結局、限定的な数を買うことになる。だから、同じ著者の本を買いがちになる。
なかなか新規開拓が出来ないのも、面白くないので、個人的な良書の条件を決めている。
それは、「ノウハウを求められている本であっても、ちゃんと物事の定義や背景の説明を書こうとしている」ということである。
本書もその例に漏れず、メインは実践紹介とノウハウの紹介であるのだが、その手前のところに、短いながらも「なぜPBLなのか」「プロジェクト学習とは何か」というようなことをコンパクトに説明してくれている。
2つめのテーマにデューイやキルパトリックの説明がされつつ、現代の学校の文脈でどうすればいいの?という話題に展開していくのが、自分の好みにとても合っていました。
High tech Highやミネソタニューカントリースクールの話も名前だけというレベルであっても出てきたのは、個人的にはテンションアップです。
※ミネソタニューカントリースクルーなどについては以下を参照。

情報時代の学校をデザインする: 学習者中心の教育に変える6つのアイデア
- 作者:C.M.ライゲルース,J.R.カノップ,Charles M. Reigeluth,Jennifer R. Karnopp
- 発売日: 2018/02/21
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
稲垣忠先生はインストラクショナルデザインがご専門ということもあるので、内容としては、インストラクショナルデザインの視点を活かして、プロジェクト学習を企画するために、教員はどんな観点から単元を見れば良いかということの説明になっています。
Chapter2で大きな枠組みが説明され、その枠組みで小中高のあらゆる実践を網羅的に紹介することで、PBLの建て付けを理解できるように工夫されている一冊です。
わずか30ページの理論解説で、後半の多くの実践をすっきりと理解することが出来、自分が授業をいざ開発しようというときに、再現性のある形で計画が出来るという仕組みになっています。
本書のポイント
本書のPBL・プロジェクト学習、つまり情報活用型プロジェクト学習のポイントは2つある。
一つが、プロジェクト学習全体の流れの骨組みとして、本書が提唱している「NADプロセス」。もう一つが、探究学習の質として「気持ちの質」「活動の質」「思考の質」の三つを観点と設定していることである。
この二つの骨組みのおかげで、本書で紹介される実践が非常にすっきりと理解できるし、自分で単元を考えようと言うときも明晰に授業を組み立てられるのである。
具体的にこれらの内容がどのようなものかは、以下の稲垣忠先生のサイトから大枠を理解することが出来る。(というか、書籍よりもWebの方が理屈の説明は詳しいかも…)
上記のサイトからNADプロセスの定義を引用すると
情報活用型プロジェクト学習を短時間でデザインできるワークショップを開発しました。「語る」(Narrate)「ほぐす」(Analyze)「仕込む」(Design)の3ステップで単元を作るので、NADモデルと名付けました。
(https://ina-lab.net/special/joker/pbl/#NADより2020年8月10日18:00確認)
このように説明されている。
本書を見ると、このNADプロセスの直前に「逆向き設計論」が紹介されている。
このことからも分かるように、NADプロセスのミソは子どもたちの探究の流れを考える際に、ゴールをできるだけ具体的に考えつつ、子どもたちの学びをシミュレートしていくことにある。
プロセスの一番最初が、「子どもの目線で探究の物語を描」くことにあるのは、個人的には好みです。子どものことをよく見立てるという仕事です。
「子どもを見る」って自分は当たり前に使うけど、これはやっぱり変な言葉で一部の界隈だけに何となく口伝で伝わるような言葉であるから、外側から見れば批判されるものだという自覚はある。ただ、もう、これはそういうものだと教育を学ぶスタート地点から教えられてきた感覚なのだ。
— ロカルノ (@s_locarno) 2020年8月6日
こういうことを前につぶやきましたが、「子どもを見る」ってどういうことなのか説明しがたい部分があるが大切だと思っています。
このNADプロセスのNで定義されていることは、一つの「子どもを見る」ということのモデルだろうと言えそうだ。
本書から広がる探究の探究
本書がよいなぁと思うのが、コンパクトながら参考文献も豊富であるし、実践例も豊富であるので、本書に色々な参考資料を組み合わせて読み深めることが出来るという点だ。
上に挙げたような書籍を参照するのも良いし、自分で実践を探してきて「これはこういう風に分析できるんじゃないか」と読むのもよいのではないだろうか。
インストラクショナルデザインのように、非常に合理的に整理されているからこそ、論点が分かりやすいし、応用もしやすい。
個人的には…

学習者中心の教育を実現する インストラクショナルデザイン理論とモデル
- 作者:C.M.ライゲルース,B.J.ビーティ,R.D.マイヤーズ
- 発売日: 2020/07/20
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
こいつと組み合わせていくのもよいかと思っています…というか、ばっちりハマるのでちょくちょく読み合わせていきたい。
職場の読書会などに、今回紹介した『探究する学びをデザインする! 情報活用型プロジェクト学習ガイドブック』はばっちりなんじゃないでしょうか。
まさに、大人が探究を探究する…そんな時の手がかりになる一冊ではないでしょうか。








 このブログについて
このブログについて
