昨日に引き続き、本の読みかたに関する覚書。
今日からリーディング・ワークショップを週に一度のペースで始めたのですが、生徒の読書の様子を見ていると気づいたことがある。
それは当たり前のことかもしれないが、本を読むスピードが個人によって大きく異なるということだ。しかも、それは普段、問題演習でのスピードとは無関係であるように見える。
本を読むスピードは、速ければ早いほどたくさん本を読めるからよいことのように思える。自分は決して本を読む速度は速くないので、どんなに頑張っても一日二桁までは届かない。院生時代にも論文を読むのが苦手でかなり苦労したわけで…。
まあ、色々な人にとって悩みの種である本を読むスピードに関して対極にある二冊の本から考えてみましょう。
読むのが得意でないからこそ早く読む!?
まずは昨日もちょっと触れたこちらの本。

遅読家のための読書術――情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣
- 作者: 印南敦史
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2016/02/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (2件) を見る
この本は帯にもあるように「1ページに5分」掛かってしまうようなスピードで読んでいたくらいの遅読家であった筆者が一日1冊以上の本を読み、書評を書き続けることができるようになったコツが書いてある。
それは「フロー・リーディング」というような読みかたであって、「読むべきではない本」や「早く読める本」をちゃんと選び、「早く読む必要がない本」に丁寧に時間をかけて読もうという考え方だ。
「早く読む必要のない本」とはストーリーのある本であり、「早く読める本」とはいわゆる新書のようなそれぞれの章で完結して読めるような本のことだという。そのような本はエッセンスを丁寧に読んでいけば、十分に理解して読んでいくことはできる。もちろん、気に入ったところを何度も読み直したりかみ砕いて読んでいったりすることは否定していないし、むしろ、気に入ったところはノートに手書きで書き出すことをおススメしている。
結局、この本も昨日話題にした『読んでいない本について堂々と語る方法』で論じていた「読んだとは何か」ということと同じような思想を感じる。
つまり、我々は読んだそばから読んだものを忘れているのだから、「ちゃんと読んだ」に束縛され、読むことが億劫になってしまうことは愚かしいということだ。だから、「どうせ忘れてしまう」のだから必要なところや自分にひっかかるところを丁寧に時間をかけて読み、そうではないところはどんどん流して読んでいこうという前向きな「読み飛ばし」「ななめ読み」をしようという主張だ。
とはいえ、なかなか「飛ばし読み」や「流し読み」については良心の呵責(笑)があるとは思うし、慣れないと要領を得ないで訳わからないことになるかもしれない。そんな人に対する処方箋としては、第一に上の『読んでいない…』を読んで「ちゃんと読める」妄想から離れることを、第二に自分に流し読みをしなければ到底読み終わらないような量の本を短期間に読むことを、第三に次のスローリーディングで本を読んでいくことをおススメする。
早く読まなくてもいいんじゃないかなという発想
作家の平野啓一郎は「ゆっくりと時間をかけて読む」ことをおススメしている。
まあ、似たような授業を灘の先生がやっていることが話題になりましたね。
灘校・伝説の国語授業 本物の思考力が身につくスローリーディング (宝島SUGOI文庫)
灘中奇跡の国語教室 橋本武の超スロー・リーディング (中公新書ラクレ)
……これは国語の授業とは言いたくないし、まったく本の読みかたには役に立たないけど*1。
話が脇にそれましたが、この本で平野氏は「本はじっくりと考えて読まれることを期待して書かれている」という作家の立場を汲んで「スローリーディング」で丁寧に読んでいくことを主張している。
ただ、一方で『遅読家のための読書術』とは、逆に「書き写すことは効率が悪い」ということや「声に出して読まない」ということを述べて、「丁寧にゆっくり読むために無駄なことをしない」というスタンスだ。
そして、読んでいくスタンスとしては「誤読」を恐れずに自分が好きなように理解しながら本を読んでいき、そんな「誤読」を含みながらも筆者の意図*2に対して近づいていこうという態度である。
それを実現するためのキーワードが「違和感」を大切にして、その「違和感」を一つ一つ丁寧に紐解いていくことを強調している。
どちらの本も結局は言っていることは同じ
百八十度逆のことを言っているように見えるが、結局は「本と自分が必要なように付き合えばいい」という発想だ。面白いことにこれは『読んでいない本について…』の中でも話題になっている<ヴァーチャル図書館>という概念で、本について人々がコミュニケーションを作り上げることが本を読むということだという話に似ている。
つまり、本を読んでいくことで自分の中にどのような観を練り上げて、最終的にそれを自分のコミュニケーションに役立てていくか、生活に活かしていくか、価値観を豊かにしていくかということに繋がっている。
本を読むということが書いてあることを正確に読み取って、何か即物的に役に立てようという発想からは大きく外れているのである。
精読を一斉授業で教えられるのか
そして、どちらの本にも共通して話題になっているのが「学校の国語」の硬直したありかたや隠されたルールについてだ。つまり「読んだ本を最後まで読まなければいけない」ということや「本を正確に読まなければいけない」ということや「読み飛ばしたらいけない」ということなどの呪縛を指している。
ここでやはり思い出すのが「読者の権利十か条」だ。

- 作者: ダニエルペナック,Daniel Pennac,浜名優美,浜名エレーヌ,木村宣子
- 出版社/メーカー: 藤原書店
- 発売日: 1993/03
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 11回
- この商品を含むブログ (9件) を見る
紹介すると以下の通り。
第一条 読まない権利
第二条 飛ばし読みする権利
第三条 最後まで読まない権利
第四条 読み返す権利
第五条 手当たり次第なんでも読む権利
第六条 ボヴァリズム(小説に書いてあることに染まりやすい病気)の権利
第七条 どこで読んでもいい権利
第八条 あちこち拾い読みする権利
第九条 声を出して読む権利
第十条 黙っている権利
まあ、国語の授業はどれも思い通りにはいかないところですよね。
逆に、上の本たちで紹介されているのはこれらの「読者の権利」について実現しようという側面が見て取れるよなぁ。
あなたはどうやって本を読みたいですか?





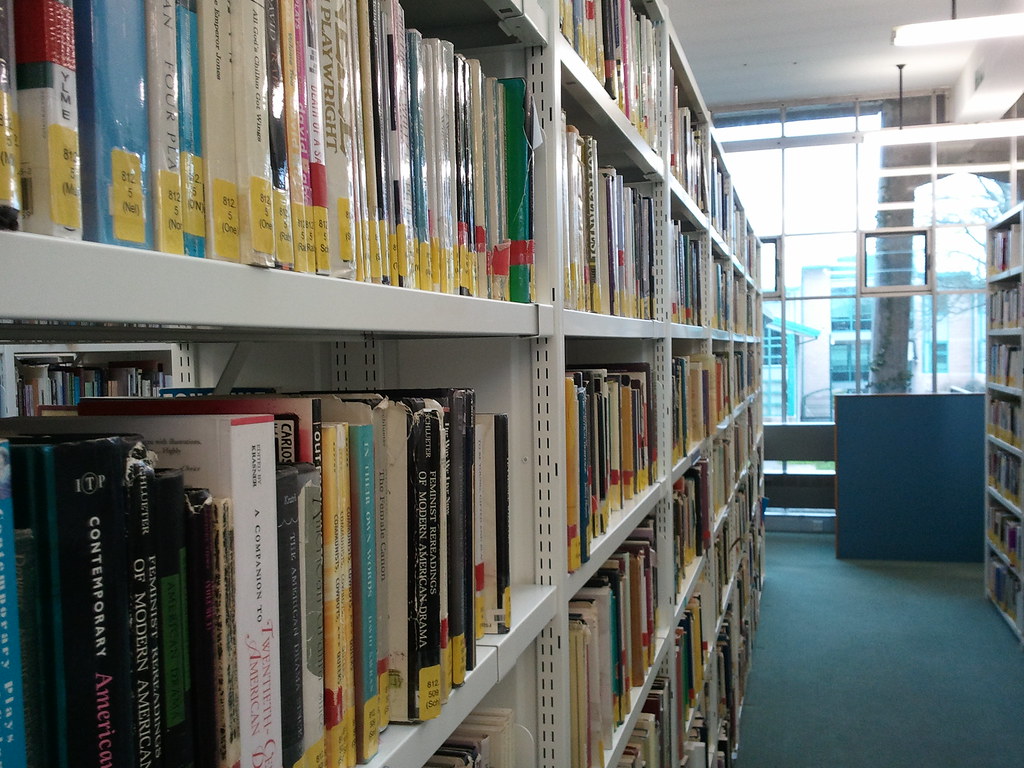


 このブログについて
このブログについて
