しばらく間が空きましたが、これが最後のリーディング・ワークショップの振り返りのまとめです。
今回はリーディング・ワークショップの最後に生徒にアンケートをお願いしたので、その結果をまとめたものを紹介します。
まあ、アンケートと言っても厳密にやったものではなく、なんとなく傾向が分かればいいかなぁという程度のものです。記名式でお願いしているし、宿題として投げているので、正確性はあまりありません。
今後、実践してみようと思う人の参考になればいいなぁと思い、簡単にまとめたものを載せておきます。
リーディング・ワークショップは自分にとって意味があった?
リーディング・ワークショップは生徒に「自由の読書をする」ことを求める授業です。ですから、読む本を指定したり読んだ本について読書感想文を書かせたりというようなことはしません。
だから、授業をする側とすれば、「本当に意味があるのか?」「勉強したいという生徒のニーズに答えられているのか」ということは気になります。
そんな思いがあったので、最初に「リーディング・ワークショップは意味があったか」ということについて選択肢と自由記述で回答してもらった。
結果としては、「とても意味があった」「意味があった」という回答のみで「意味がなかった」という回答はなかった(結局、記名式のアンケートの影響だろうけど)。
自由回答の内容は以下のようなことが書かれていた。
- 読書の頻度が授業に限らず、明らかに増えた
- 記録を取ることで発見があった
- 段々と読むスピードが早くなった気がする
- 好きな本を何度も読めて、その本の良さを発見できた
- たまたま出会った本で自分の関心が広がった
- 忙しくて本を読む時間がなかったので助かった気分
- ジャンルを気にして読むようになった
- 自分の関心のある分野の本を手に取れるようになった
- 自分にでも読める本があることに気づけた
- 読書が苦手だと思っていたけど、そうでもないと気づいた
- 知識が増えたような気がする
色々な意見はあるけど、個人的に重要だと思うのは二点。
一つ目は「忙しくて本を読めなかった」という意見が多く、リーディング・ワークショップを通じて本を読む時間ができたことで、日常生活でも読書をしたくなるという意見が多かった。
これは、リーディング・ワークショップで読みかけの本ができるということが大きいと感じる。少しでも本に手を付けているとその続きを読みたくなったり関連する本を読みたくなったりするということだろう。見ていてもシリーズものにはまった生徒は授業外の時間でも本を読んでいた印象はある。
まあ、そうはいってもテスト前の大福帳を見ると「テスト勉強で全然本が読めない…」という愚痴が多くなっており、たぶんリーディング・ワークショップから離れれば離れるほど読書の量は減ってしまうのではないかなぁ…とは思う。
もう一つは「読書が苦手だと思っていたけど、自分でも読書ができた」という意見だ。要するに食わず嫌いならぬ読まず嫌いをしていたということだろう。
どうして「読書」が嫌いになってしまったのかということをちゃんと生徒に聞いてみてもいいかもしれない。書いてきた内容から推測すると、自分のレベルにあっていない文章ばかり読まされてきたということではないか感じる。
「自分は国語が苦手だと思っていた」「自分にも読める本があるんだ」そんな意見を読むと、国語の授業が「読書」ということから遠ざけるようなことをしているのかもなぁ…と反省。
リーディング・ワークショップによって読書量は増えた?
9割の生徒は「読書の時間が増えた」とうことを言っているけど、残り1割は「授業の分だけ増えた」という回答だった。
やはり、高校生は忙しい。本当に色々な本を読んで欲しいと思うのであれば、授業の時間を生徒に手渡さないといけないなぁと思う。
少しでも本を手に取る時間ができれば、そこをペースメーカーに本を読むきっかけくらいはできそうではないかなぁ。
ミニ・レッスンは役に立ちましたか
これも記名式のアンケートなので「役に立たなかった」とは書いては来ない(笑)
重要なのは、一緒に尋ねた「役に立ったミニ・レッスンはどれですか」という項目。生徒が「役に立った」という回答が多かったのは次の項目。
- 読者の権利十か条
- 日本十進分類法(NDC)
- 本の種類と内容の特徴
- 並行読書と積読について
- 優れた読書家の技法
こうして並べてみると皮肉だけど、「国語の授業」では普通はやらないようなことのほうが生徒からの人気が高い。
これらの項目の中でも「読者の権利十か条」と「並行読書や積読について」の話は特に「役に立った」という回答とコメントが多い。
「読者の権利十か条」については「途中でやめていい」ということが、特に生徒にとっては新鮮だったらしく、この話があったからこそ、リーディング・ワークショップが苦しくならないでよかったとうコメントもあった。
また、「並行読書や積読」については、普段の授業でやっているような精読からすれば、なんとなく後ろめたい感じがしていたというが、並行読書や積読をやってみることで読める本の数が増えたのが嬉しいという意見があった。
「優れた読書家の技法」については、一つ一つの項目が重いし、広いので「もっと詳しく知りたい」というコメントを受けたものの、実際にやってみようと思った生徒は多く、「読解力が向上する」という感覚と結びついているようだ。
カンファランスはどう思いますか?
自分の最大の課題だったカンファランス。
これについては項目への回答とコメントをもらった。
この項目は他の項目と違って、マイナスな?回答として「集中力が途切れる」「何を話したらいいかわからない」という意見が少なからずあった。
実際、本を集中して読んでいるところに話しかけられたら、話が分からなくなってしまうし、楽しいところを邪魔されたくないという気持ちはよくわかる。こういう思いを抱かせるとは予想できたので、「どうやってやるべきかなぁ…」と悩んでいた。
しかし、思いのほか肯定的な回答も多くあったので、紹介しておこう。
- 読書の技が分かる
- なぜ自分がこの本を読み続けているか考えるようになる
- 本の評価を考えるようになり漫然とした読書じゃなくなる
- 本に関する話題や視点が広がる
- 眠気が覚めたり集中力が取り戻せる
- 単純に、本の内容について話すのが楽しい
カンファランスをやっている方として意外だなあと思ったのが「本について話すのが楽しい」という意見の多さ。
自分の好きなものであれば、意見を話してみたり相手からのコメントを聞いてみたいということだろうか。
個人的には読書の技に関することや読書に向かうときの視点みたいなことを話したかったので、それが少しでも伝わったのはよかった。
ただ、まだまだ、考えないとぎこちないかなぁという感じはする。
リーディング・ワークショップでどんなことが学べましたか?
自由記述で、自分の成長したことについて考えて答えてもらった。
- 何を考えて読むといいとか知れるのはいい
- 関連付けたり予想したりする読み方を知れた
- 自分の読書の癖や傾向などに気づいた
- 自分にも読める本があることが嬉しかった
- 読み切らなくてもいいとわかって、いろんなジャンルの本を手に取れるようになった
- 他人に薦められても本はあまり読まないものだと気づいた。自分でちゃんと選ぶべき。
- 生まれて初めて本を途中で読むのを放棄したような気がする。
- 自分の読む本のジャンルの偏りに気づいたので他の本を読もうと思った
- 行きづらかった図書室に通うことができて色々な本と出会えた
- 司書さんのすごさが分かった
- 図書室で借りることでいろんな作家やジャンルの本を手に取れた
- 人生の中で一番感動した本に会えた
- 複数の同時読みという技
- 友達と紹介しあうことができた
- 読書仲間が増えると嬉しい
- インターネットより情報が濃密なこと
- 友達と読んでいる本の交流会ができた
色々な意見があったけど、一つ一つの分析も面白いところだけど、それ以上に、学んだことが一人一人異なることに良さを感じた。
カンファランスに対する不安やリーディング・ワークショップが「本当に意味があるのか」となる不安などはどれも根本には「本当に生徒がちゃんと学べるのか」という不安であるし、「今まで教科書で指導してきたものを手放して「遊び」ではなく「学び」になるのか」というような不安があった。
でも、上のような生徒の回答を読んだら、そんな不安もバカバカしくなるし、それ以上に、自分が「全員に対して何かしらの最低限度の基準は教えるべき」という思いに捕らわれているんだなぁと感じる。知識や必要なことを伝えることを手放してしまうのは無責任ではあるけど、必要なことは教えなければならないと強硬な態度になるのも、生徒一人一人が異なることを豊かに学んでいる様子を見ると、バカらしくなる。

ようこそ,一人ひとりをいかす教室へ: 「違い」を力に変える学び方・教え方
- 作者: キャロル・アントムリンソン,Carol Ann Tomlinson,山崎敬人,山元隆春,吉田新一郎
- 出版社/メーカー: 北大路書房
- 発売日: 2017/03/17
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
一人一人がこれだけ異なることを、画一的にやるよりもずっと手ごたえをもってやっているのを見てしまうと、もう一度、授業で「何かを伝えなければいけない」ということを固く考えるのを見直さないといけないかなぁと思う。
リーディング・ワークショップはどうやっていけばいいと思いますか?
生徒に率直に「普通の授業とリーディング・ワークショップのどちらが大切?両方やるならどんなバランスがいいと思う?」と聞いてみた。
そうしたら以下のような意見を得られた。
- リーディング・ワークショップで読書の時間を持てること自体に価値がある
- 読書家の技を好きな本で学んだら、色々な分野の文章を普通の授業で読むときにその技が使える気がする。
- クラスで読書している人が明らかに増えたのが分かったのでやったほうがいい
- 授業ではなく自分でやらなければ意味がないから、授業でリーディング・ワークショップをやるのは、この一年以上は不要
- 「この話は前に読んだ本に似てる!」とか思うようになるので読書は多いほうがいい
- テスト前などはむしろ勉強したい
- 日ごろいけない図書室に行けるのがいい
- 古典や進路関係の本が読める機会になるので貴重な時間
- 読書だけでは模試や入試で点数が取れないのではないか
- 進学校である以上は授業できちんと指導してほしいこともある
- 受験生になった時に自分が読書しているイメージが持てないので、普通の授業も大切にして欲しい
- 週に1度くらいの今のペースであれば、やっていきたい
- ただの内容解説の授業はできるだけ取捨選択して、リーディング・ワークショップをやってもいいのでは
- 朝読書の時間などがあればリーディング・ワークショップはいらないのでは?
- 図書室をふらふら眺めていることにも意味があったから時間は欲しい
- 時期的に早い学年で始めるといいかも。受験は受験指導で。
- 一時間丸ごとではなく、毎回10分とかでやるのがいいかも。
- 各人が大切さに気付けばいいから、授業でやらなくてもいいこと
- 普通の授業を中心に進めて、授業で考えるための思想や知識を身に付けるために自由読書の時間を定期的に入れるのがいい
- 好きな本ができれば自分で勝手に読むようになるので、好きな本を見つけたら授業中心でいい
- 月1くらいのペースならいい。
- 入試に出題された本など課題図書を指定されて読むということもしてみたい
まあ、色々な意見がありますね。
リーディング・ワークショップとは設計が違う方法が合うんだろうなぁという子どもの意見がある一方で、今よりももっとリーディング・ワークショップをやりたいという子どももいる。
印象的なのが「週1くらいがいい」という意見がすごく多かったことだ。生徒からは「週1くらいなら授業も困らないと思う」という意見が多かったが、授業をしている方の立場からすれば年間で40時間くらい持っていかれると考えると大変な授業数だと感じるわけです。でも、体感的にはそのくらいまとまって本を読む時間があっていいと思っているんだろうなぁ……。
リーディング・ワークショップを通じて自分が学んだこと
結局、一人一人が求めていることや前向きに勉強できる方法は違うということに尽きるのだろう。自分がいったい何を大切にしたいかが問われている感じがする。
一人一人が本当に楽しそうに学んでいる姿や、生徒のコメントから伝わってくる熱量を感じると、中途半端な授業はダメだなぁ…と思う。
たぶん、折衷でやっていくのは下策。いったい、自分がどこに立ち位置を置いていくことになるんだろうと思う。
自分が大きく苫野先生の考え方に影響を受けていることを改めて感じる。
「一人一人が違う」ということを認めてあげたいということと「自由であること」を他のことよりも優先し、尊重したいのが自分という人間だと思う。





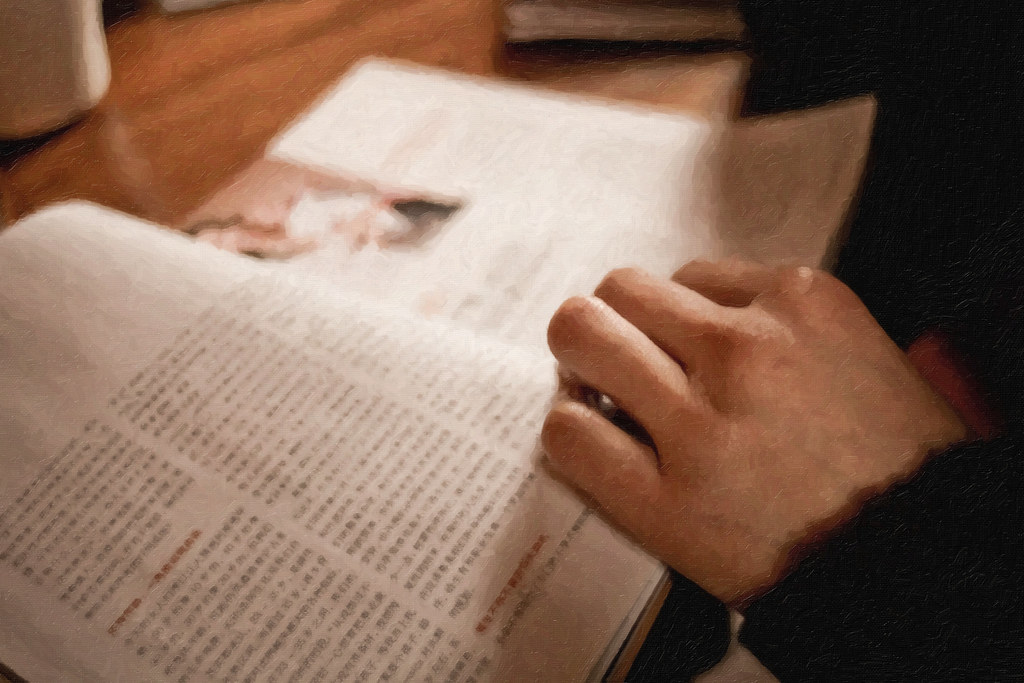

 このブログについて
このブログについて
