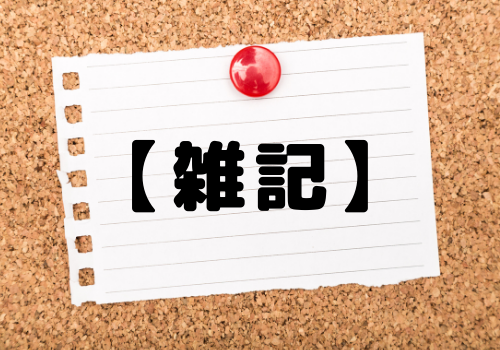
そろそろ新年度のカリキュラムのことも考えています。自分がどこに配置になるかはよくわかりませんが、予想できる範囲でどんな展開ができるかを考えています。
毎回、心配している
ちょうど、昨日の記事に書いたように、授業の準備はすればするほどに心配が増えていく。そして、小賢しい策を弄すると、たいてい生徒の良さを損ねて、反省することになるのである。
学年で一クラスだけを教えているわけではないので、同じ内容の授業を複数回行うのが普通で、同じ授業を何度も行っているのだけど……それでも、授業の前は気がそぞろになる。
どうしても自分の授業には自信が持てない。どうしても授業で生徒に委ねる部分が多いので、余計にどうなるか毎回ドキドキする。ちゃんと生徒の見取りが出来るようになれば、もっと自信をもってやれるものなのだろうか。
授業の名人と呼ばれる人たちの教室に共通する、あの落ち着いた雰囲気になかなか自分がたどり着けないでいるという気持ちが強い。
解説は気が楽
逆に解説が多いところは、比較的気が楽なのである。
生徒との知識の差があるからこそ、技術的なことをちゃんと訓練すれば、授業としてはそれなりに見栄えはするし、安定してどこまでいけるかは予想できる。
授業の起承転結を考えることも、教材の見立てであったり、生徒の理解度を把握したりと、一方的にただ喋っているのとはわけが違うのである。何年も同じ板書案を使え回せるほど授業は甘くはない。
同じ文章で授業をするとしても、その時々の話題で扱い方は変わってくる。文章がどこかに抽象的に存在しているものではないのだ。色々な話題と関連性を持って意義が立ち上がってくるのである。
そういうつながりを理解する時に、やはり入試問題は非常に参考になる。
準備にはそれなりに時間はかかるが、安定した結果を出せるように思う。まあ、それでも見立てを誤って沈痛となることがあるので、注意が必要であるが……。
毎日が楽しみであり、不安である
授業を作るのは、楽しみである。他の人に簡単に外注したくなることはない。いくら非合理と言われても、自分で今の生徒の様子を見ながら、よい教材だって作りたい。
そうして、自分のオリジナルを晒すと言うことは、非常に精神が削られることである。生徒の反応をみて毎日、一喜一憂なのである。






 このブログについて
このブログについて
