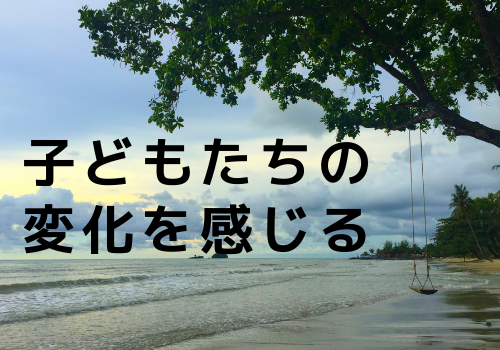
ろくろく授業研究する余裕もなく、流されてきた四月がそろそろ終わる。
新入生たちと新しく授業に取り組んできた二週間。
三年前とは少し生徒の気質の変化があることを感じています。
「学力」とは無関係に…
一番、強く感じるのが、生徒のいわゆる偏差値のような「学力」とは無関係に、話合いに前向きに取り組もう姿勢が比較的多くみられることである。
ただし、その一方で決して話合いに対して前向きな気持ちを持っているわけではない。
姿勢としてはしっかりと取り組めるのに、気持ちとしては前向きではない。
この矛盾したような生徒の在り方が、どうも今年、受け入れた生徒たちの気質らしきものに見える。おそらく、小学校、中学校でもかなり色々な話合いの訓練を受けてきたのだろうと思う。生徒たちが中学校などで総合学習で何をやってきたのかということを尋ねると、なかなか高度なことまでやっている生徒が少なからずいる。
高校の中にいると、あまり中学校、小学校の動きが見えないでいるが、確実に取り組みが変化しているし、影響を与えているのだと思う。
話を元に戻そう。
色々な取り組みの結果、生徒は確かに話合いの姿勢は上手くなっているのだろう。しかし、決して前向きな気持ちにはなりきれていないということは注意しておかないといけないと思う。
この本をやっと読み終えましたが、一つ一つの実践例が生徒の自尊心を損ねることなく、注意深く生徒の気持ちを引き出すような内容になっていることを確認しなおさないといけないなぁと感じています。
話合いで「発言はする」けれども「受け止められたと思わない」、「ちゃんと聞こうと思う」けれども「自分が置いていかれた気がする」、そんなネガティブな感覚を持っているのを丁寧に解きほぐしていかないといけないなと思う。
授業も工夫されているなぁ
生徒から中学校時代にどんな授業を受けてきたのかという聞き取りをイチイチしている。自分の興味関心に基づく調査である。
まあ、生徒からの口伝えなので、どこまで実態が掴めているかは怪しいけれども、色々と面白い話が聞けている。先生たちの苦労を余所に、生徒は割と好き放題いうのですよね…(泣)。
しかし、でも、これも三年前に比べて、色々な授業の工夫が聞けて楽しいです。
例えば、QFTをやったことがあるという生徒がいたりします。

たった一つを変えるだけ: クラスも教師も自立する「質問づくり」
- 作者: ダンロスステイン,ルースサンタナ,Dan Rothstein,Luz Santana,吉田新一郎
- 出版社/メーカー: 新評論
- 発売日: 2015/09/04
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (6件) を見る
ワークショップ型の授業をやったことがあったりPBLという言葉を知っていたり……完全に数年前とは違うんだなと思う。
同じことを漫然とは繰り返せない
生徒がこれだけ色々な体験をしてきているのであれば、自分の授業が同じようなことはできないなと思う。
中学校までの体験が上手く行っているかどうかともかくとして、そういう体験をしてきた生徒が色々な能力を身につけ、色々な思いを抱いていることに注意して向き合わないといけないだろうと思う。
周囲を見ていると愚痴っぽく言えば、これだけ小中とやっていることが変化しているのに、どうして高校はこうも開き直って旧態依然を正当化できるんだろうなぁ……。






 このブログについて
このブログについて
