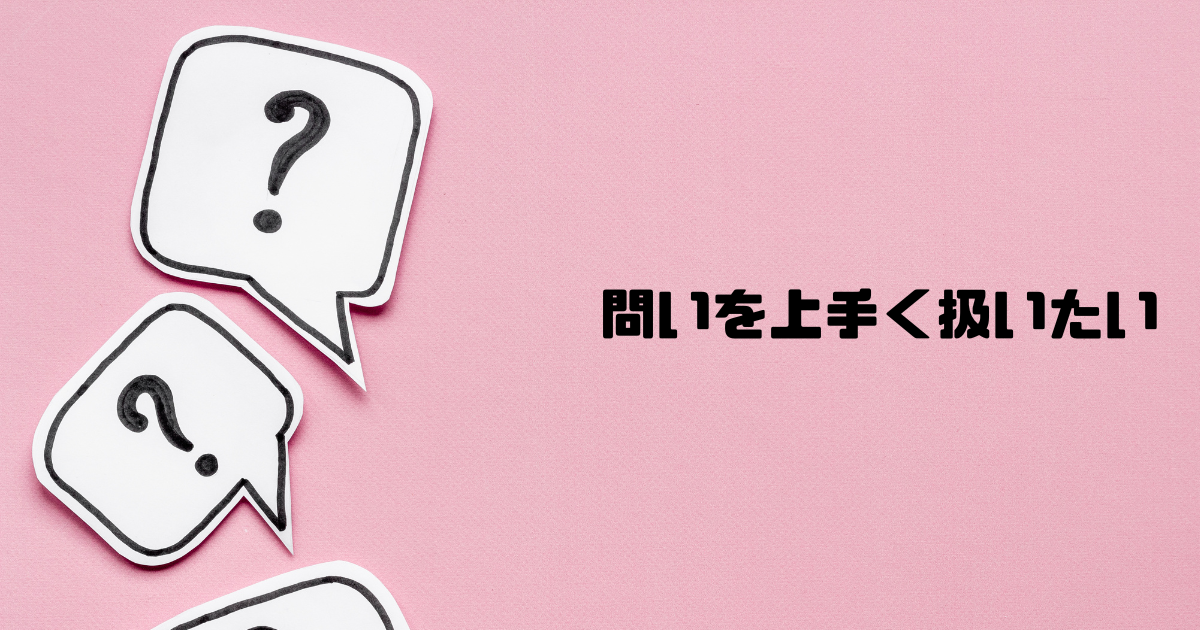
三学期の授業が「こころ」と大がかりにやることになるので、どうやろうかとあれこれと検討中です。
じっくりと読みたい
「こころ」を扱うのであれば、じっくりと生徒と読みたいという気持ちがある。高校卒業時に一冊、このくらいの本を自分たちで問いを立てながら必死に読んだという読書経験が、上手くその後の読書生活につながって欲しいという気持ちはある。
文学的な読みを深めるというよりも、とにかく粘り強く表現にこだわる練習ができればなぁと思うのである。一見すると意味不明なことも少し時間をかけて読んでいけば、自分で解釈に気づけるような、そういうことを大切にしたいのだ。
「こころ」をやるときにはしっかりと読み直すのがこの本だ。やっぱりシンプルながら、しっかりと読めるように生徒が成長している姿が目に浮かぶ。
どうすればこういう領域にたどり着けるのだろう?
問いを手がかりに
やはり生徒にとって馴染みにくい題材である「こころ」を読み進めていくためには、最初は適切な「問い」を手渡す必要があるだろうと思っている。その意味で本日なんとなく再読しているのがこちら。
問いの形や狙いを参考にしつつ、授業の展開を悩んでいるところだ。
あと『続・その問いは…』の「こころ」の実践は11時間とかなり長大に時間を取っていることとどうしても「教科書」の掲載部分に重心を置いているので、一冊を通して……という観点からすると、そのまま安易には使えない。工夫のしどころである。
読みの方略的な側面については…
生徒に自力で読んでもらいつつ、もう一つの軸として「ミニ・レッスン」で上手く読みの技法や方略を伝える必要があると思っている。
そのミニ・レッスンの整理に、今回は非常に心強い一冊がある。
この本の中で紹介されている技法の一つ一つはこだわり出すと「ミニ」レッスンではなくなるので、どう捌くか……結構、頭を使わないとこれは難しい。
YouTubeをどうするか…
だいたい、現状の生徒の動きを考えると、「こころ」を読んで自力で解釈できないと、YouTubeなどで解説を探し出す。
YouTubeの解説は使ったことがない人が思うほどにはいい加減なことは言っておらず、ほどほどには筋は合っているのだけど、そこに頼ってこられてしまうと、あまり話は広がらないだろうと思っている。
油断すると全員が同じ動画を見て話し合っているみたいな状況に陥るので、そうなるともはや本を読んで語り合う…という状況ではない。
特に制限をする必要は感じないが、問いかけの仕方を間違えると意味が無いことになりそうだ。何が分かれば「読んだ」ということになるのか……そういうことを考えないといけないのだろう。









 このブログについて
このブログについて
